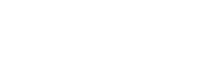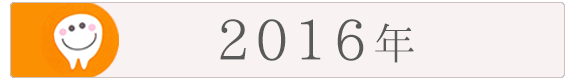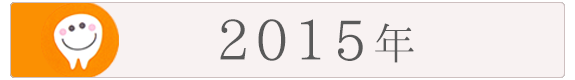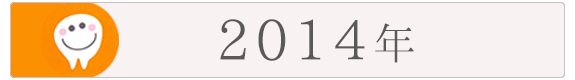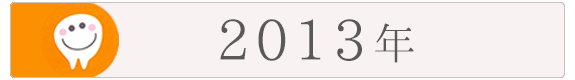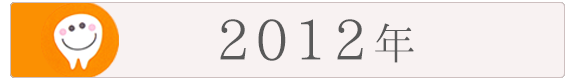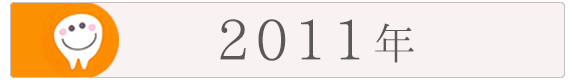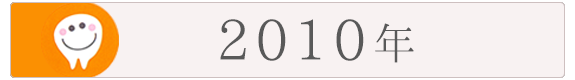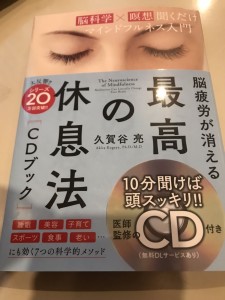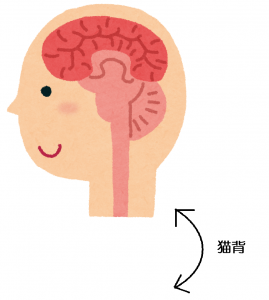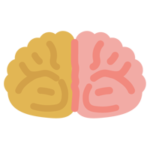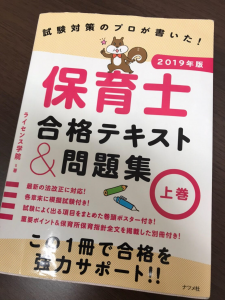時間軸で考える!!
「よく考えなさい!!」とか昔からよく言われました!!
でも、当事者にとってどう考えたら良いかわからない・・・と言うのが本音でしょう…。
僕自身も学生の頃より本当に成績が悪くて苦労していました。
しかしある日、大変頭の良い梅本君に
「お前は、行きあたりばったりやねん!!」
「もっと、時間軸で考えへんからそんなやねん!!」と指摘されました。
つまりですね、期末テストの例で言うと

それぞれの①、②、③の時期に何をしておくのか?
何が重要なのか?
をまず考える!!という事です。
そして前日は、その①、②、③の復習だけにあてる!!
という事です。
まずは、そこをしっかり考えるところから始める。
この事は、今でも僕の生活スタイルにもなっています。
旅行や仕事、プライベートの予定でもまずは時間軸でざっくり考えてから行動するようにしています。
ex)

梅本君のお陰でちょっぴり成績があがりました。梅本君ありがとう(^-^)
(ちなみに梅本君は今は某病院の外科部長をしています。)

理事長 山田 武史